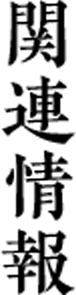ひれ酒とは、数多ある日本酒の飲み方のひとつです。ふぐや鯛などの鰭(ひれ)をあぶり焼き、燗酒に入れたものを言います。
米不足によって世の中に質の悪いお酒が流通していた昭和20年ころ、お酒をより美味しく飲むための工夫として生まれました。
漁師がたまたま焼いたひれを熱燗に入れたところ、出汁が出て美味しくなることを発見したのが発祥と言われています。
実際にひれ酒は、日本酒の旨み成分グルタミン酸とひれの旨み成分イノシン酸が相乗効果を発揮して、強い旨味を感じる組み合わせ。
なかでもふぐのひれを使用したひれ酒は別格とされ、濃厚な風味を味わうお酒の楽しみ方として、現在でも変わらず日本中で楽しまれています。
下関酒造の「ふくのひれ酒」は、山口県下関市では飲食店・観光地土産売り場などで広く販売され、地元民が愛してやまず、全国のひれ酒ファンも魅了しているロングセラー商品です。
ひれ酒専用のお酒を特別に仕込むこだわり、ふぐの王様・とらふぐの焼きひれを贅沢に丸々1枚入れた演出、ふぐの濃厚な旨味と日本酒が見事に調和した味わい、そしてふぐのイラストがキュートなカップ。冬はもちろん、年間を通して飲みたくなると評判の、自慢の商品です。
年間販売本数は10万本以上! 高級感のある白磁カップはギフト用やお店でのご提供に、お手頃で飲みやすい透明ガラスカップはご自宅用にと、さまざまなニーズに応える多彩なラインナップもファンを惹き付ける秘訣になっています。

●下関酒造のふくのひれ酒が選ばれるポイント
ふくのひれ酒は「本場下関の料亭の味をご家庭で」というコンセプトから開発された商品です。多くの方に本場下関のひれ酒をお手軽に、美味しく飲んでいただくための技術、工夫を隅々にまで凝らしています。
1.とらふぐのひれを使用しています。
ふぐの中でも市場価値の高い虎河豚(とらふぐ)のひれだけを使用しています。
高タンパクでアミノ酸含有量も多いため、とくに強い旨味を感じることができます。
他社製品にはひれのエキスだけを使用しているものもありますが、下関酒造のひれ酒は、ひれそのものを入れた本物のひれ酒にこだわりました。
独自の焼き上げによって旨み成分や香ばしさが濃厚となっており、最初の1杯を飲んだ後に新たに熱燗を注げば、もう1~2杯ひれ酒を楽しめるほどです。
2.ひれ酒専用の日本酒を仕込んでいます。
ひれの味わいを引き立てるため、ひれ酒専用日本酒を仕込んでいます。
焼きひれの芳醇な香りが際立ち、スープのようなまろやかな旨味を楽しめるように、端麗で香味にクセがないお酒を醸造しています。1杯、もう1杯と呑みたくなる美味しいひれ酒の秘密は、この専用酒にあると言えるでしょう。
3.ふくのひれ酒のための特別なカップです。
ひれ酒は、燗につける温度が重要です。75℃~80℃くらいの熱めの温度がひれ酒には適しています。しかし、温度が足りないと生臭さが残ってしまい、自分で調理するのはなかなか手間になります。そのため下関酒造では、お手軽に本場の味を楽しんでいただけるように、電子レンジで簡単に燗付けできる特注カップ(白磁・透明ガラス)を採用しています。もちろん湯煎で燗付けすることも可能です。
燗付けしたふくのひれ酒は、アルコールのツンとした感じや酸味も和らいでおり、熱燗が苦手な人にも「スープのように飲みやすい」と絶賛されています。
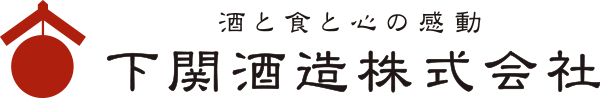 下関酒造 うまい酒作りの原点がここに
下関酒造 うまい酒作りの原点がここに